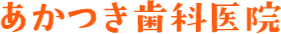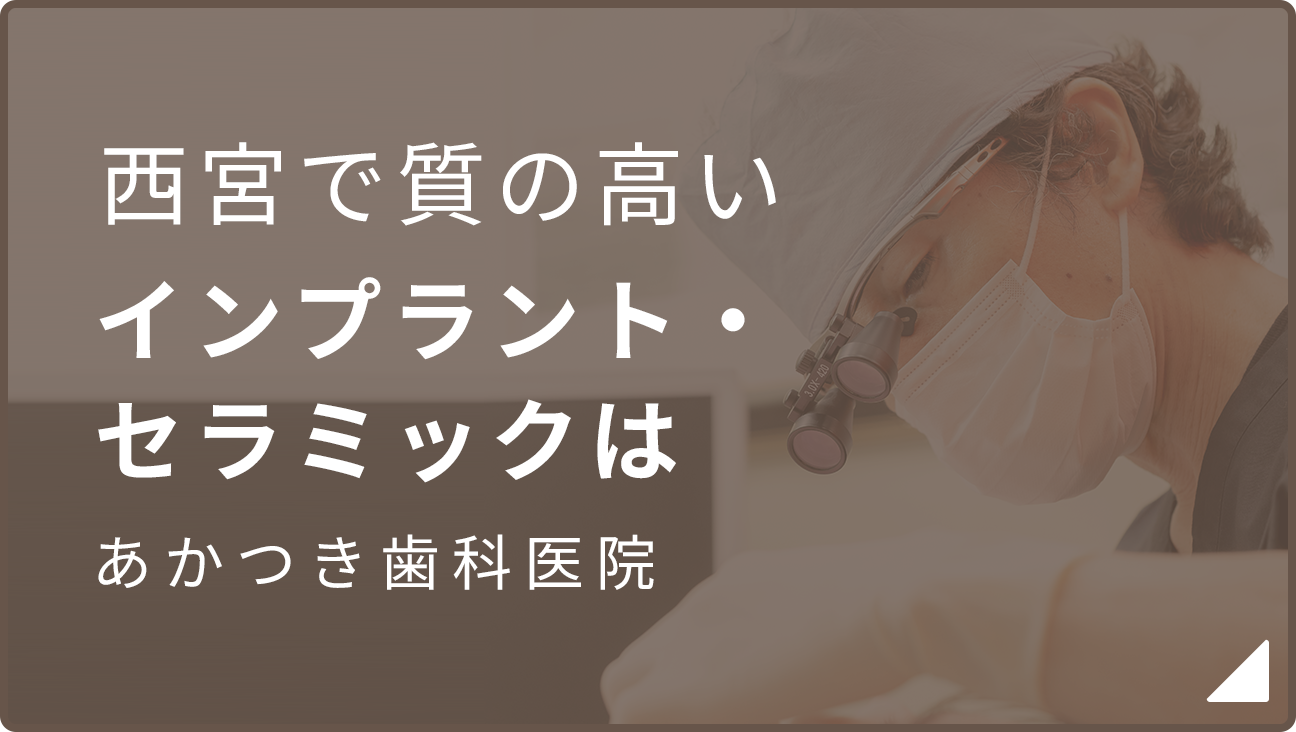医院ブログ



- 2022/08/02
- 歯科コラム
横向きの親知らずの抜歯は必要?歯科医師が解説
西宮市にある歯医者さん、あかつき歯科医院です。
親知らずと言えば、抜歯が大変とイメージされる方は少なくないと思いますが、実際のところどうなのでしょうか。
今回は、横向きに生えている親知らずの抜歯についてお話ししていきます。
横向きになっている親知らずとは?

横向きになっている親知らずとはどんな状態なのでしょうか。
通常、歯は頭の部分が真っ直ぐになって生えています。
しかし横向きの親知らずの場合は、この頭の部分が、手前の歯に向かう形で横を向いて生えている状態です。
横向きの親知らずの抜歯の必要性

横向きに生えている親知らずは、何も症状がなくても抜歯する必要があるのでしょうか。
一般的に親知らずを抜いた方が良いのかどうかは、親知らずがあることによって悪影響がでているかどうかが基準となります。
例えば歯が顎の骨の中に埋まっていて、それ以上生えてくる見込みがない時や、抜かない方がメリットが大きい時などは、わざわざ抜歯をする必要はありません。
親知らずの抜歯にはメリット、デメリットがあり、次の通りです。
抜歯のメリット
�@歯磨きがしやすくなる
�A虫歯や歯周病のリスクを下げられる
�B歯茎が腫れる・痛むなどの症状が出ることがない
�C親知らずが原因で歯並びが悪くなることを防げる
抜歯のデメリット
�@抜歯による痛みや腫れなどが生じる
�A傷口が治るまで食べかすが詰まりやすくなる
�B下の顎にある神経が通る管の近くに歯が埋まっているような難しい症例の場合、そこに傷がついてしまう可能性がある(まれにしびれや麻痺などが生じることもあります)
このように親知らずの抜歯には、メリットとデメリットどちらもあります。
そのどちらが大きいのか検討した上で、抜歯をするのか残しておくのか決めていくことになるでしょう。
自分の場合はどうなのか?お知りになりたい方は、ぜひ西宮市のあかつき歯科医院にご相談ください。
横向きの親知らずを抜歯するのは難しい?

「親知らずを抜くのが大変だった」「顔が腫れた」などという話を聞かれることもあるでしょう。
特に横向きに生えている親知らずの場合は、真っ直ぐ生えている場合と比べて、抜歯は難しいと言えます。
通常のように頭の部分を掴んで抜くことができないため、歯茎を少し切ったり、歯をいくつかに分けて取り出したりする必要があるからです。
しかし、同じ横向きでも一人ひとり生え方や状況は異なるため、一概に大変だとは言い切れません。
少し手間はかかりますが、比較的スムーズに抜歯できることもあります。
反対に、下の顎にある神経が通る太い管に近かったり、それを抱え込むような形で親知らずが生えている場合は、難しい抜歯となることが多いでしょう。
親知らず抜歯後の痛み・麻酔の期間

親知らずを抜いた後の痛みや麻酔の効果はどうなのでしょうか。
抜歯をするということは、少なからずお口の中に傷ができる状態になるため、全く痛みが生じない、ということは残念ながらありません。
しかし、処方される痛み止めを服用すれば抑えられる程度ですし、お口の中は治りが早いため、1週間もすれば気にならなくなることがほとんどです。
麻酔の効き目は麻酔の種類や個人差によっても異なりますが、だいたい2、3時間〜下の親知らずを抜歯するために深いところまで効かせる麻酔をした場合は約6時間ほど続きます。
痛みが苦手な方や心配な方は、麻酔が切れる前に痛み止めを飲んでおくと、麻酔が切れた後も楽に過ごせるでしょう。
親知らず抜歯後に気を付ける事
親知らずを抜歯した後は、どんなことに気を付けたら良いのでしょうか。
麻酔が切れるまでは感覚がなくなっており、唇や頬を噛んだり、火傷をしたりしてしまいがちです。
飲食は麻酔が切れるまで控えていただいた方が良いでしょう。
また、傷口を舌や歯ブラシなどでなるべく触らないようにすること、傷口が気になるからと言ってうがいを頻繁に行わないことも大切です。
お口の中も、手などを怪我した時と同じように、血が固まってかさぶたのようになり治っていきます。
この時にいじっていたり、うがいをし過ぎてしまったりすると、なかなか血の塊ができずに痛みを生じる原因となってしまいます。
食べかすが抜歯したところから中に入ってしまうということもありませんので、暫くは歯ブラシも傷口に当てたりしないようにしましょう。
まれに血の塊が上手く出来ず「ドライソケット」という状態になることがあります。
ドライソケットになると、傷口が覆われないため強い痛みを生じてしまうため、抜歯後の傷は気になると思いますが、少しの間そっとしておくようにしてあげてください。
さらに、麻酔が切れた後はお食事を通常通りしていただいて構いませんが、傷口が安定するまではしみるような刺激のあるものは避けた方が無難でしょう。
西宮市のあかつき歯科医院では口腔外科出身の医師が抜歯を行います。

院長経歴
院長の荒木 暁と申します。
私は甲南大学経済学部、北海道医療大学歯学部を卒業後、歯科医師になりました。
親知らずの抜歯は難しい場合もあり、専門の歯科医師のいる大きな病院を紹介されるケースも珍しくありません。
しかしながら、私は県内公立病院・口腔外科にて外来や病棟、麻酔科と多くの症例を経験しており、その後一般歯科や審美歯科、インプラント専門医への勤務を経て今に至ります。
口腔外科の経験も豊富にございますので、皆様にはご安心いただければと思います。
万が一当院での治療が難しいと判断した場合は適切な医療機関を紹介いたします。
抜歯が怖いという方へ
歯を抜くことに抵抗がある方は少なくありません。
あかつき歯科医院では、なるべく痛みを感じずに抜歯ができるような治療を心がけております。
そのため、次のような場合は「全身麻酔」での抜歯を提案させていただくこともあります。
・どうしても抜歯が怖い方
・4本一度に抜いてしまいたい方
・お体の具合で、抜歯に何らかの影響がある方
この場合、基本的には1日入院していただくようになりますが、全身麻酔下ですので意識がないのはもちろん、抜いていることも痛みも感じない状態で終わります。
迷っている方はぜひ一度、西宮市の歯医者「あかつき歯科医院」へご相談ください。
下記の記事でも、親知らずの紹介をしております!
よろしければ、続けてご覧ください!
- この記事の担当者
-
院長荒木 暁